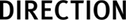菅政権に期待できるのか? EUが自問する「日本の子供拉致」問題
Rafal Olechowski / Shutterstock.com
◆欧州議会による対日決議
批准した条約内容を守らない日本に業を煮やした欧州議会は今年7月8日、日本に対する厳しい決議を採択した。内訳は、賛成686票、反対1票、棄権8票という圧倒的多数による決議だ。その主張は次の通り。まず、欧州議会は、「日本の親による実子の拉致増加に危惧の念を抱く」。そうして、日本は「子供の拉致について国際ルールを遵守していない」と考え、日本に「連れ去られた側の親が(中略)子供たちに近づき訪問する権利について裁判所が下した決定を効果的に執行するよう強く要請する」。さらに、「日本の欧州連合国民である子供たちは、彼らの権利を保障する国際協定が提供する保護の恩恵を受けなければならない」ことを強調する。
かなり厳しい表現で書かれたこの決議について、茂木敏充外務相は7月14日に記者質問に答える形で、「日本としてはハーグ条約の対象となる事案については、(中略)一貫して適切に対応してきている」と発言したのみだ。つまり、日本が国際規約を遵守していないという指摘は正しくないという認識を示した形だ。
◆共同親権と単独親権の違い
この双方かみ合わない主張の根っこには、離婚後の親権制度の違いがある。日本以外の先進国では、離婚後も父母双方が共同親権を持つのが通常なのに対し、日本では離婚後は一方の親にだけ親権を認める単独親権制度をとっている。そのため、ほかの国では、到底あってはならない「拉致」を実行する親が、日本では罪に問われることすらない。フランス2の番組内でインタビューを受けた日本の法学者、山本和彦教授は、「子供の連れ去りを推奨しているわけではないが(中略)、これは我々の法制度の派生と言える」問題だと認めている。同教授の言葉は、日本の一般的な空気を良く表している。曰く「日本では母親による子供の連れ去りは誘拐とは見なされません。深刻な犯罪とは見られないのです。日本では「誘拐」とは呼ばず「遠ざけ」と呼ばれます。良いことではありませんが、犯罪でもないのです」というものだ。「法律の改正も必要だが、人々の意識を変えるのが先決だ」とも言えよう。
実は、日本でも父母の離婚後の子供の養育のあり方を検討する動きはある。その証拠に、今年4月には「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」が法務省民事局から発表されている。ただ、その動きは速いとはいえず、法の改正を待っていては、現在連れ去られている子供たちは成人してしまうのではないかと思える。