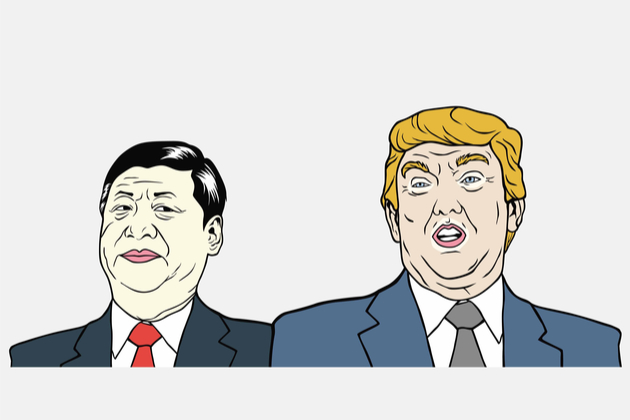米国の衰退を印象づけた訪中トランプ氏の豹変ぶり 欧米メディアから失望の声
3Dsculptor / Shutterstock.com
トランプ米大統領は、アジア歴訪の旅の3ヶ国目である中国を訪れ、習近平主席から特別待遇で迎えられた。これまで対中貿易に関し厳しい姿勢をアピールしてきたトランプ氏だが、訪中時には批判どころか中国を擁護する発言まで飛び出し、欧米メディアを落胆させた。習氏と和やかなムードを作り出したものの、期待された強いアメリカを示すことはできなかったようだ。
◆対中強硬派から一転して擁護へ
トランプ氏と言えば、大統領選の選挙運動中、対中貿易赤字に憤り、為替操作国認定や多大な関税を課すことも辞さないと訴え続け、多くの支持を集めていたことが思い出される。今回の訪中でも「残念なことに、(米中貿易は)とても不公平で一方的なものだ」と述べたが、「結局のところ、中国を責めはしない。自国民の利益のために、他国を利用する国を、誰が責めることができよう」と言った後、「私は中国を大いに讃えるが、現実として、こんなに制御できない貿易赤字を許した(アメリカの)過去の政権の方を責める」と述べ、責任を以前の自国の政権に押し付けてしまった。
これには欧米メディアもあきれてしまったようだ。APは、中国は貿易でアメリカを「レイプ」したとかつて宣言したトランプ氏は、好戦的な自分のスタイルを捨ててお世辞と盲従を選択し、経済的不均衡を過去のアメリカ大統領のせいにしたと冷やかだ。ニューヨーク・タイムズ紙(NYT)も、約束通り貿易不均衡を是正しなければというプレッシャーに加え、北朝鮮問題への協力も求めなければならなかったためか、トランプ氏は習氏の前では、より懐柔的な調子であったと解説している。
米民主党上院議員チャールズ・シュマー氏も、トランプ氏の発言を猛批判している。「大統領は中国を責めないかもしれないが、私は責める。そして大統領に投票した数百万人のアメリカ人、中国の強欲な貿易政策のため職を失った人々もだ」と述べ、「選挙運動中は、中国の貿易慣行にライオンのように反対したくせに、大統領は今や羊レベルだ」と断じた(政治誌『The Hill』)。
◆中国に媚びて実を取る。これもトランプ氏の戦略?
コロンビア大学の政治学者、アンドリュー・ネイサン氏は、これまでさんざん中国を批判したトランプ氏だが、実は今回を見れば対中戦略などあまりないことが分かると指摘する。反対に、トランプ氏のソフトなアプローチは、中国の協力を誘導するための戦略と読むこともできるという声もある。元CIAの副次長補、デニス・ワイルダー氏は、貿易、北朝鮮問題ではトランプ氏はプライベートで率直かつ直接的だったとし、リーダー間の個人的つながりを確立するのは両国にとって大切だと述べている(AP)。
米シンクタンク、戦略国際問題研究所のボニー・グレーザー氏も、習氏に媚びて、中国国民を褒めることで、今後のポジティブな結果につながる友好関係を築こうというのがトランプ氏の明らかな戦略だと述べる。しかし、中国は完全に北朝鮮を見放してはおらず、アメリカが懸念する「略奪的」貿易慣行に対応するとも思えないため、これがうまく行くかどうかは疑問だとしている(AP)。
◆独裁国家でも気にしない?訪中はアメリカの衰退を示した
今回の訪中に際し英ガーディアン紙は、トランプ氏は従来の民主的な同盟国より独裁的な国家訪問のほうをエンジョイするようだと述べている。自身の訪中のため、嫌がらせを受け軟禁される活動家や反体制派がいるのに、たとえリップサービスとしてでもトランプ氏は人権問題には興味を示さないと批判する。また習氏が気候変動抑制に率先して取り組んでいるのに、パリ協定も脱退し、世界のリーダーの役割から手を引くことで、アメリカは中国におみやげを与えているようなものだと断じる。
高圧的な交渉人のトランプ氏が、外国で対立することを避けたのは今回が初めてではないとAPは述べる。トランプ氏はサウジアラビアで人権侵害に言及せず、「過激なイスラムのテロ」といった言葉も使わず、2016年の大統領選干渉について、ロシアのプーチン大統領には控えめな批判しかしなかった。12日からのフィリピン訪問では、違法な殺人を認める麻薬戦争を監督するフィリピンのドゥテルテ大統領をたしなめないことをホワイトハウスは示唆しており、結局、これまで公に咎められたのは、ほかでもない古くからの欧州の同盟国で、しかも理由が「NATOの分担金の支払いが十分でない」だったと、APは皮肉たっぷりに説明している。
ガーディアン紙は、今回はさながら「ブロマンス」とでも呼べそうなほど、トランプ氏は習氏を褒め称えたと報じている。トランプ氏の意図は明らかではないが、手のひらを返したような大統領の態度は、アメリカへの失望と新たな超大国としての中国の台頭を、多くの人々に感じさせたようだ。