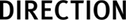CO2ゼロで作る「ターコイズ水素」、欧米で実用化向け開発
Modern Hydrogen
水素は、使用時に燃やしても水になるだけで二酸化炭素(CO2)を排出せず、環境負荷が少ない。そのため「次世代のエネルギー」といわれている。
日本では、水素を使う燃料電池自動車(FCV)の保有数は7千台を超え、水素ステーションは全国に150ヶ所以上ある。また、家庭用燃料電池のエネファーム(天然ガスから取り出した水素を利用して電気が作られ、排熱で給湯や暖房も行う)は2023年に累計販売台数が50万台を超え、水素は一部の人たちの間で少しずつ身近な存在になってきている。
2024年5月には、いわゆる「水素社会推進法」が成立し、低炭素水素などの事業者に政府から助成金が交付されることが決まった。「2050年の年間供給量2000万トン」到達を目指し、今後、水素エネルギーの商用化が加速すると期待されている。水素エネルギーを得るには、さまざまな方法がある。
◆水素製造過程でのCO2排出が課題
現在、国内外で水素の製造に使われている原料のほとんどは、石炭や天然ガスなどだ。これらは化石燃料のため、水素を取り出す際(水蒸気を使用)に多量のCO2が排出される(天然ガスのほうが石炭より少ない)。水素の燃焼時にはCO2が発生しないとはいえ、脱炭素の観点からいうと矛盾が生じている。この水素は一般に「グレー水素」と呼ばれている(水素は無色で、「グレー」は製造方法の大まかな分類を示すラベル)。
この問題を解決するのが、グレー水素の製造工程で出たCO2を回収・貯留・利用する方法だ。CO2排出を相殺しているため「ブルー水素」と呼ばれる。
さらに、製造時のCO2排出ゼロで地球に優しい水素も作られている。水を原料とし、太陽光発電などの再生可能エネルギーを使って水素と酸素に分解する。これが「グリーン水素」だ。しかし、グリーン水素はコストが高い点がデメリットで、現在世界で進んでいるプロジェクトのうち数年後に実現するのは、たった1割強にとどまるともいわれている。
そして、同じく製造時にCO2を出さない「ターコイズ水素」もある。ターコイズ水素の原料は天然ガスの主成分のメタンや、バイオガス(バイオマスを発酵)由来のメタンだ。メタンを再生可能エネルギーで熱分解して、水素と同時に固体炭素を作る。この固体炭素はタイヤや建材に利用するなど産業分野で役に立つ。
ターコイズ水素は日本でも研究が進んでいるが、欧米での開発は急ピッチだ。先進的な例を見てみよう。
◆米国:「天然ガスと水素」のブレンドをガス会社の既存インフラで供給
アメリカのモダン・ハイドロジェン(2015年設立)は、水素製造技術の開発に取り組むスタートアップ企業で、ビル・ゲイツなどから投資を受けて成長してきた。同社のモジュール式の水素製造装置「MH500」だと、1台1日当たり500キロのターコイズ水素の製造が可能だ。副産物として出る固体炭素は舗装や道路補修用のアスファルトの材料になる。
同社の水素製造装置は昨春、約200万人の顧客を持つ天然ガス会社NWナチュラルの施設内に設置された。プラントで生成されたターコイズ水素は天然ガスと混ぜ、既存のインフラを使って顧客に届く。「天然ガス+水素」を使えば、従来のように天然ガスのみを使った時よりもCO2排出は少なくなる。

NWナチュラルの施設内に設置された水素製造装置|Modern Hydrogen
「天然ガス80%+水素20%」の混合ガスにした場合、天然ガス100%に比べCO2排出量は最大7%削減されるという。NWナチュラル の脱炭素化ディレクター、クリス・クローカー氏によると、7%削減は年間40万トンの削減に相当する。CO2排出削減に貢献したいNWナチュラルの姿勢は評価できるが、気になる点もある。同社は混合ガスの供給について州の委員会や顧客に対して通知していないといい、不安を抱えている住民も多い。(オレゴン・キャピタル・クロニクル)
提携先を広げるモダン・ハイドロジェンは今年に入り、ワシントン州で最も古いエネルギー会社のPSEとも提携した。PSEは約120万人に電気を供給し、90万人以上に天然ガスを供給している。この提携により、PSEは商業および産業(鉄鋼やセメント製造など)分野の顧客がオンサイトで天然ガスからターコイズ水素を製造することを促進していく。

回収した固体炭素で道路の穴を埋めるビル・ゲイツ氏|Modern Hydrogen
◆フィンランド:「欧州最大のターコイズ水素プラント」開設
フィンランドでは昨秋、ヨーロッパ最大のメタン熱分解プラント(ターコイズ水素製造装置)がオープンした。ハイカマイトTCDテクノロジーズ(2020年設立)が建設したこのプラントは、フル稼働すると年間2000トンの水素を生成でき、同時に6000トンの固体炭素を回収できる。回収した固体炭素は、リチウムイオン電池やタイヤの製造に使われる。CO2削減量は、天然ガスを使った場合は年間最大1万8000トンだという。
メタン熱分解プラントでは、水を電気分解する「グリーン水素」と比べ、エネルギー使用量が少なくて済むことも利点だ。ハイカマイトTCDテクノロジーズの技術では、電気分解時のエネルギーの13%でターコイズ水素を生成できる。
なお、モダン・ハイドロジェンもハイカマイトTCDテクノロジーズも、日本の企業が出資しているのは興味深い。

フィンランドの商業規模プラント建屋|Hycamite

プラント内部の設備|Hycamite
◆日本:水素+回収したCO2を有効活用
日本では、上記の水素の色分けには入っていないが、CO2は発生しつつも有効活用して水素を作る方法が注目を集めている。原料は、家畜の排泄物や下水汚泥といった廃棄物系バイオマスだ。
北海道では、牛の糞尿(ふんにょう)を発酵させて水素を作っている。排出されるCO2からはギ酸(飼料を保存するための添加物)を製造できる。ギ酸はほとんどを輸入に頼っているため、地元で製造可能なことはメリットだ。一方、福岡市は民間企業と連携し、それをFCVなどに供給する水素ステーションを運営している。
将来、水素社会が本当に実現するのか。刻々と変化する水素エネルギー製造の話題は今後も注視したい。