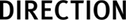南極半島から離脱した東京都と同じ規模の氷山 海底で新種を発見
画像はイメージ(Flicker/ Mark Brennan )
南極半島で離脱した氷山によって、ぽっかりと空いた海域を初めて調査した研究チームは、その深海に非常に豊かな生態系が存在していることを発見しました。
海洋科学の発展と深海探査の推進を目的とする非営利団体「シュミット海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)」が発表しています。
未知の生物多様性が存在していた南極大陸の棚氷の下
南極半島の南西側に位置するベリングスハウゼン海では、シュミット海洋研究所の国際調査チームが調査を続けています。
チームメンバーは、ポルトガル、イギリス、チリ、ドイツ、ノルウェー、ニュージーランド、アメリカから集まった科学者たちです。
2025年1月13日、「A-84」と名付けられた東京都とほぼ同じ大きさの氷山が、南極半島の氷床に付着している巨大な浮氷のひとつ「ジョージ6世棚氷」から離脱しました。
調査チームは、シュミット海洋研究所の遠隔操作可能な無人探査機「SuBastian」を使って、25日に新たに露出した海底に初めて立ち入ることに。
8日間深海底を観察した結果、水深1,300mの深海には、氷魚、巨大なウミグモ、タコ、サンゴや海綿など、豊かな生態系が存在していたのです。
これまで、南極大陸の棚氷の下に何が棲んでいるのかはほとんど知られていませんでした。
2021年、英国南極地域観測所の研究者たちは、南ウェッデル海のフィルヒナー・ロンヌ棚氷の下に底棲生物の痕跡があることを報告したのが、初めてのことだったそう。
深海の生態系は通常、表層からゆっくりと海底に降り注ぐ栄養塩に依存しています。
一方、南極の生態系は何世紀もの間、厚さ150メートル(約500フィート)の氷に覆われており、表層の栄養塩から完全に遮断されています。
海流も栄養分を移動させるため研究チームは、海流が氷床下で生命を維持するメカニズムの可能性があると仮定していますが、正確にはまだ解明されていません。
しかし、研究チームは豊富な生態系で、いくつかの新種を発見したそうです。
氷床は、気候変動によってここ数十年の間に縮小し、質量を失っています。
科学チームは、生物学的・地質学的サンプルの採取に加え、氷河の雪解け水がこの地域に与えるさまざまな影響を調査しているとのこと。
今回の発見は、南極氷床の浮遊部分の下で生態系がどのように機能しているかについて、新たな洞察を与えるものだとしています。