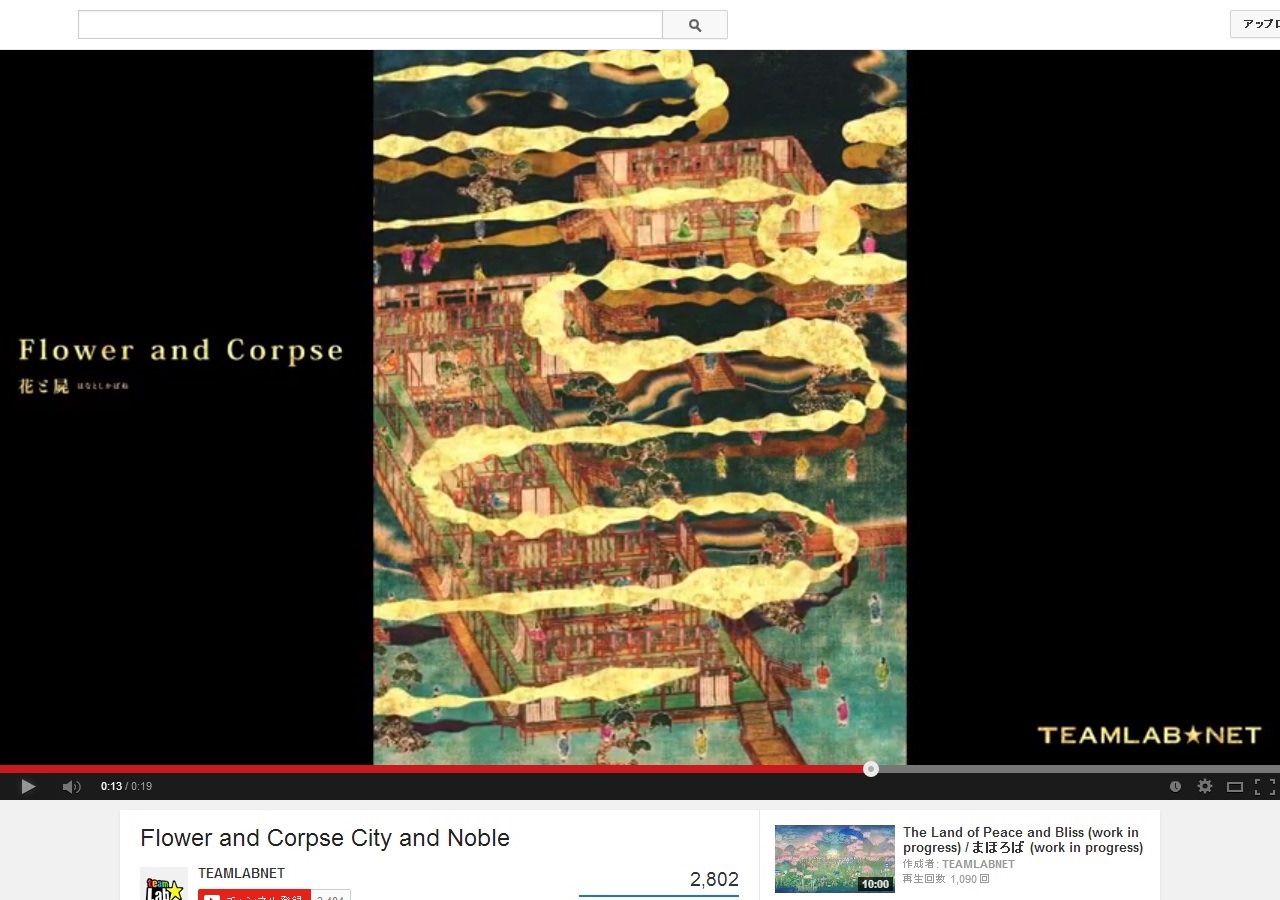日本のメディアアートは“創造性と消費と伝統のカオス” 海外紙が注目する最先端の作品とは
現代、日本人の生活は、テクノロジーと切っても切り離せないものになっているため、アートにおいても、テクノロジーをテーマにした作品、あるいは手法として用いたメディアアートが、日々生まれ続けている。
【テクノロジーが現実世界に浸透していく。アートでも】
ガーディアン紙の記事は、日本は、創造性と消費と伝統のごちゃまぜだと言う。また、アートと文化とテクノロジーを融合させることにかけては、最も卓越している、と語る。
インターネットは日々の生活に欠かせないもの。しかし、2012年に第1回が開催されたフリーマーケット「インターネットヤミ市」で出品された品物は、一癖も二癖もあるものばかりのようだ。主催のIDPW(通称アイパス)は「100年前から続く、インターネット上の秘密結社」を名乗り、「インターネットが降臨する場」を作る活動を行っているという。このフリマも、もちろん“オフライン”で実際に人が集まって行われるものだ。
ガーディアン紙はこのイベントを紹介し、その出品物をいくつか挙げている。「グリッチ刺繍」、「インターネット・フレイバー・コーヒー」、「現実世界リツイート」などだ。「グリッチ刺繍」は、コンピューターミシンの刺繍用データをいじり、意図的にデータ破損を起こしたもの。読み込みに失敗した画像データのような効果が、布の上で忠実に再現されている。「現実世界リツイート」は、ガーディアン紙の説明によると、出品者が購入者のメッセージを、フリマ参加者に向かって叫ぶ、というサービスらしい。
NPO法人CANVASは、店頭で販売中のテレビ、駅や空港のスクリーンなど、全国6000ヶ所以上の公共空間のディスプレイ装置で、子供たちの描いた絵を表示する「街中“こどもテレビ”プロジェクト」を、2011年に実施した。記事はこのプロジェクトも紹介している。他にも、テクノDJジェフ・ミルズのサウンドトラックに合わせて、地球のデータが刻々と映し出される、日本科学未来館の大型球形ディスプレイ「Geo-Cosmos」など、さまざまなアート作品が紹介されている。
【コンピュータープログラムが絵を発展させる?】
ニュー・サイエンティスト誌は、名古屋大学の鈴木泰博准教授のチームが開発したプログラムを紹介している。自然選択を模した遺伝的アルゴリズムによって、これまでにない絵画作品を発展させるというものだ。
鈴木准教授らは、絵画の手法が世代を通じてどのように伝えられていくかを研究し、それをプログラム化したという。「今日まで残っている絵画は、すでに存在していたモチーフを、拡大・縮小し、回転し、複数組み合わせることによって描かれています」と准教授は語る。このことが、親の特徴が子に受け継がれつつも変化を生じる、生物進化の過程をまねているように見えた、と記事は伝える。
このプログラムでは、まず初めに好きな美術様式を指定する。次に、保存されている画像の中から、アルゴリズムで処理させる絵を選択する。絵は、半分に切ったり、他の絵に重ね合わせたりと、さまざまに変化させられる。結果として出てきた絵は、ユーザーが最初に選択した様式にどれほど忠実に沿っているかに応じて、間引かれるか、保存されるかのどちらかだ。そしてこの過程が繰り返される。
記事は、芸術作品の制作において、プログラムが人間の代わりになるものではないことを強調している。コンピューターを使った制作を行うあるアーティストは、「アルゴリズムが助けとなるのは、興味深い結果を生み出す可能性があるシステムや状況を作り上げるところです」と語る。また、鈴木准教授は「人と機械の組み合わせは、新しい芸術を生み出す可能性を持っていると思います」と語る。どちらも、予期せぬ化学反応により、創作の原動力となることを考慮しているのだろう。
【テクノロジーの未来は暗い? 明るい? ニューヨークで開催の2つの展覧会】
美術批評サイト『ハイパーアレジック』の評論記事は、ニューヨークで同時期に開催された、日本人アーティストらによる展覧会を2つ紹介している。『存在の二重性――ポスト・フクシマ』と、チームラボの『超主観空間』だ。この2つには、テクノロジーの暗い未来と明るい未来という、対照的なコンセプトがある、と記事は語る。
記事は、現代アートにおける「日本らしさ」の、西欧での一般的な受け取られ方は、1980年代に、「キッチュな雑種性」、「原初からの自然」、「テクノロジーの洗練」を三角形化することで確立された、という上智大学国際教養学部の林道郎教授の説を紹介している。今日なお、人気のある(特に商業的に人気の)日本の現代アートは、その三角形の中のどこかに位置づけることができるという。とはいえ、この記事で主に注目しているのは「テクノロジーの洗練」である。
記事によると、福島の原発事故によって、インターネットの持つ脱物質性への信仰が、重大な転機を迎え、堅固な物質性への回帰がもたらされた、というのが『存在の二重性』が示唆する雰囲気だという。「主催者あいさつ」には、人々は自分たちの身体性に、否応なしに気づかされた、という趣旨の表現が見られる。また、この展覧会では、テクノロジーの高度化への信頼が、疑問に付されているという。
一方で、『超主観空間』では、同じものが惜しみなく称賛されている、と記事は解釈する。展覧会の中心的展示は『追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点 – Light in Dark』という作品だ。7台のプロジェクターとスクリーンが設置される。その中で、色とりどりのカラスの群れが、絶え間なく方向を変えつつ高速で飛ぶと、やはり色とりどりの飛行機雲が軌跡として残る。視点も激しく動き回る。制作者のチームラボによると、これは、アニメーションの世界で有名な、大量のミサイルが発射される際の演出「板野サーカス」のオマージュであるとのことだ。
メディアと芸術―デジタル化社会はアートをどう捉えるか (集英社新書) [Amazon]