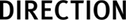中国、GDP低成長続くも工業生産など伸びる―景気底打ちか?―
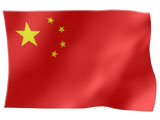
海外各紙は、中国の景気が底を打ったのかどうか、その後急速な好転が起こるかどうかについて意見が分かれているが、政府が大きな景気刺激策を打ち出す可能性は薄れたとの見方は共通している。
Financial Timesの報道姿勢―落ち着きはしたが低調続く―
現在の世界経済の成長はアジア、特に中国が牽引しているという背景において、「世界経済成長への最大の脅威のひとつは遠ざかりつつある」と報じた。
しかしそれでも、1999年以来最低の成長ペースに乗ったままであり、以前のような2桁成長へ向けてすぐにV字回復するとは思われず、世界各国から中国への原料輸入ラッシュは終焉しつつある、と慎重な見方である。
コスト高騰と設備過剰に起因する民間投資の減衰が問題であるという。
The New York Timesの報道姿勢―第4四半期に好転「する」―
やはりGDP2桁成長は当面望めないとしつつも、FTとは異なり、次の第4四半期には中国経済が目に見えて好転「する」との意見を取り上げている。
バブル再燃を警戒する中国政府は、2008年後半の大型刺激策とは違ってマイルドな方針を取っているものと説明し、これが実を結びつつあるとして、楽観的な論調である。
The Wall Street Journalの報道姿勢―「底はまだ先」、政府の無策疑う―
第3四半期(今回)または第4四半期で景気は底打ちとなり来年は回復する、と分析するアナリストたちを紹介しつつも、全体に景気回復には懐疑的であり、借り入れ需要が弱く「底はまだ先」と語る銀行幹部の観測を伝えた。
さらに、中国政府の経済管理能力を疑い厳しく批判した。具体的には、薄熙来氏のスキャンダルや11月の政権委譲の対応にかまけ、これといった景気刺激策が取られてこなかったこと。意図的な移転政策の結果、建設・不動産および関連業界の苦境が増したこと。大規模プロジェクトを幾つも承認したが資金調達に無頓着であることなどだ。政策の効果を確認してから次へ進みたい、という温家宝首相の発言についても、11月の政権委譲が「新たな緩和ラウンドの触媒になるという希望を“ダンピング(投げ売り)した”」と表現し、消極的姿勢を強調した。