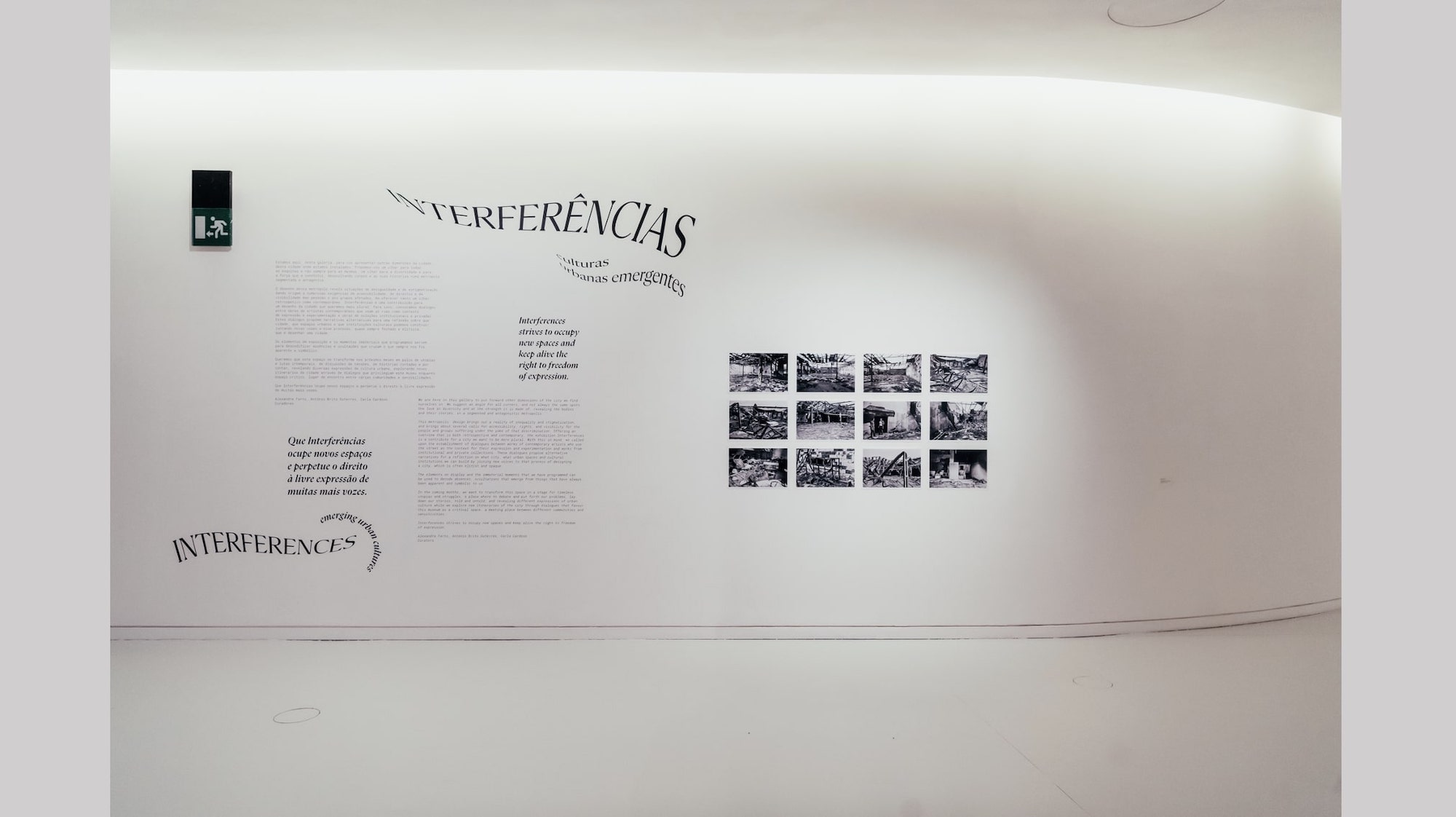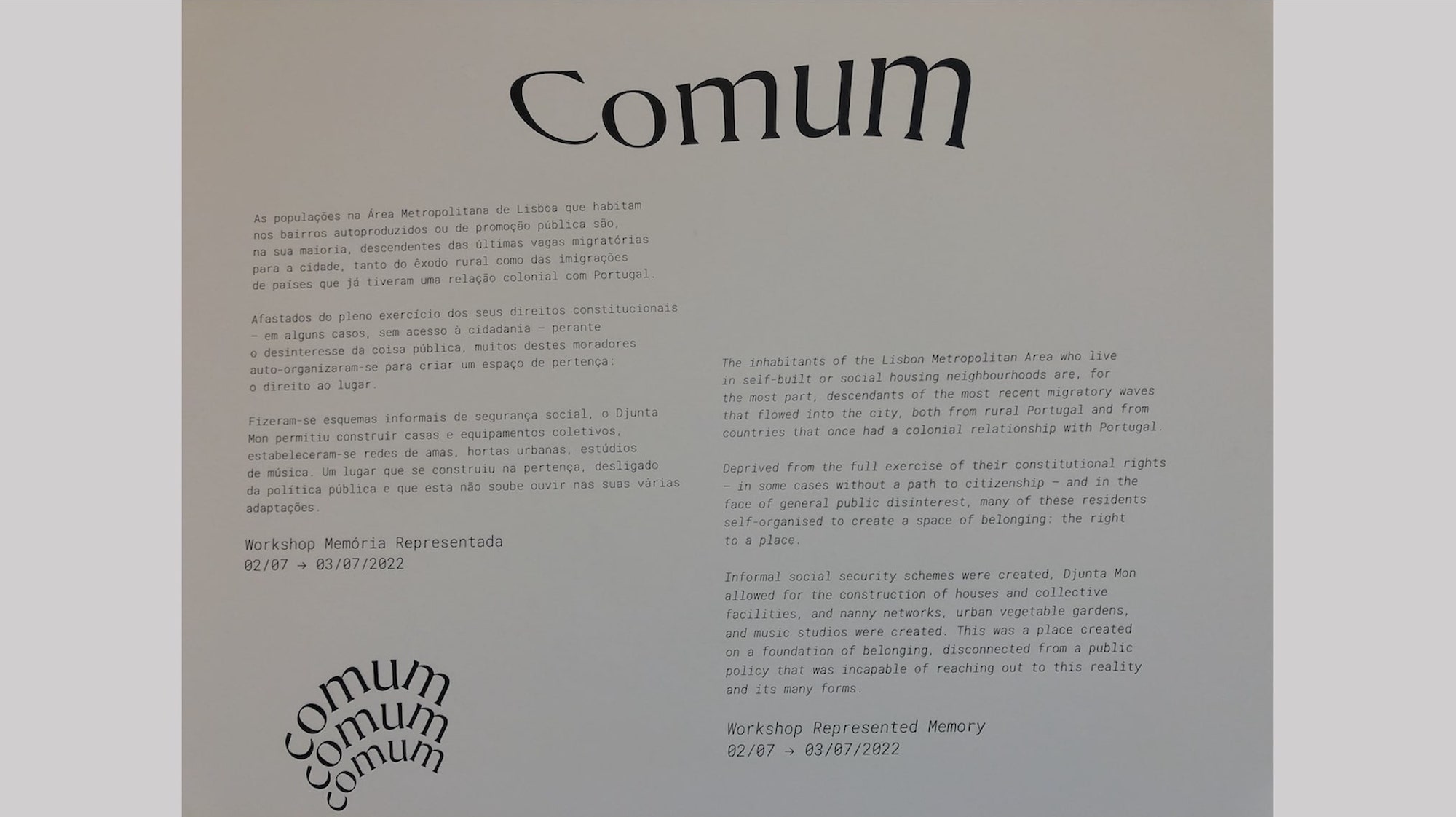ポルトガルの首都リスボンのベレム地区にあるmaat(Museum of Art, Architecture, and Technology)は、2016年10月にオープンした比較的新しいミュージアム。電力発電所として使われていた建物と新たに建設された建物が描くユニークなランドスケープと、対話を促す展示内容が魅力だ。記事では、MAATおよび企画展示を紹介する。

maat
Francisco Nogueira
海岸沿いに位置する白い陶器の建築
maatはポルトガル・リスボンを本拠点に事業展開を行う大手エネルギー企業のEDP(Energias de Portugal、エネルジアス・ドゥ・ポルトガル)が2004年12月に設立した非営利団体であるEDP財団が所有・管理するミュージアムだ。財団は、持続可能な開発を軸に、社会、文化、テクノロジー、教育、環境、遺産の保護を推進・開発・支援することを使命としている。

旧電力博物館本館 ©︎FG + SG
maatは、EDP財団の代表的な取り組みだ。20世紀前半のポルトガルの工業建築を代表する建物の一つであるテージョ発電所をリノベーションした建物と、アマンダ・レヴェット(Amanda Levete)が率いるイギリスの建築事務所AL_Aがデザインしたコンテンポラリーな建築で構成される。3.8ヘクタールの敷地内全体のランドスケープ・デザインは、レバノン出身の建築家ヴラディミール・ジュロビック(Vladimir Djurovic)が手がけた。
新設された建築には、1万5000ピースのセラミック・タイルが使われている。陶器タイルを用いたスタイルはポルトガルの伝統的な建築に見られるものだが、maatの外観はコンテンポラリーな景観を作り出している。白い流線的な建築デザインは印象的でありつつも、リスボン・ベレム地区の景観に馴染んでいる。建物の天井にあたる部分はパブリック・スペースとなっており、緩やかにデザインされた屋根を登ると、テージョ川沿いのウォーター・フロントの景色を展望することができる。

maat ©️FG + SG
イマーシブな映像作品
筆者が訪問した4月末にmaat新館で開催されていた企画展示の1つが、ポルトガルのグラフィティ・ストリート・アーティスト、アレクサンドレ・マヌエル・ディアス・ファルト(Alexandre Manuel Dias Farto)、通称ヴィールス(Vhils)が手がけた「プリズマ(Prisma)」と題された映像作品だ。Prismaは、ヴィールスが過去数年間かけて世界9都市で記録した映像を湾曲したいくつかの大型スクリーンで見せるという作品である。

サンプリングされた都市は、北京、上海、香港、マカオ、シンシナティ(米国オハイオ州)、ロサンゼルス、リスボン、パリ、そしてメキシコ・シティだ。展示は、maat新館の入り口から下の階につながる楕円形のスロープとその壁際にそって展開される。壁には、いくつかの大型パノラマ・スクリーンが、壁の湾曲した形に沿って設置されていて、来場者は映像の中に吸い込まれるようなイマーシブな体験を得ることができる。

©︎José Pando Lucas
各都市のストリートでサンプリングされた映像は、スローモーション映像として加工され、来場者はその都市における疑似体験を得ることができると同時に、同時にいくつかの場所に存在しているような異次元空間を味わうことが可能だ。グローバル都市のラビリンスを歩くことで、来場者はグローバル都市におけるアノニミティ(匿名性)を再認識するとともに、リフレクションを促される。

Alexandre Manuel Dias Farto 「プリズマ(Prisma)」
イマーシブな空間は、あまり近づきすぎると酔ってしまいそうになるが、都市と人々の動きを捉えたスローモーションな映像には、ずっと眺めていたくなるような魅力がある。都市のストリートをキャンバスに作品を展開するストリート・アーティストであるヴィールズならではの視点が、作品をより魅力的なものにしている。

Alexandre Manuel Dias Farto 「プリズマ(Prisma)」
見えざる都市の創造力
maat新館のもう1つの企画展示が「Interferences(干渉・妨害)」と題されたグループ展示だ。この展示は、これからのアーバン・カルチャーをテーマにした展示で、約50のアーティストが参加している。
Interferencesは、「アーバン・カルチャーに関するさまざまな表現を肯定する展示」であると説明されている。リスボンの都市を特徴づけるメインストリームのナラティブでは、必ずしも触れられることのない人々、地域、クリエイティビティなどにスポットライトを当てることで、改めてリスボンの多様性を提示する狙いがあるようだ。また、ミュージアムという場を対話のプラットフォームとして、必ずしも普段はミュージアムとつながりのないような人々をも巻き込むという試みでもある。会期中は、作品の展示だけでなく、さまざまなワークショップ、トークイベント、ツアー、パフォーマンス、スクリーニングといったイベントが開催。こうしたイベントは、多様な市民とアーティストとのさらなる対話を促し、都市の過去・現在・未来に関する議論をより活発化・具体化する有効な手段だ。
アフリカ系の人々はリスボンのアーバン・カルチャーを形成する主要なグループだ。ポルトガルの独裁体制を終わらせた1974年のクーデター、カーネーション革命後、70年代から90年代にかけての移民の多くはアフリカ大陸からやってきた人々だ。リスボンにはすでにもともと奴隷として連れてこられた人々にルーツをもつアフリカ系の人々がコミュニティを形成していたが、新しく移民としてやってきた人々が加わり、アフリカ系コミュニティはよりアーバン・カルチャー形成において、より存在感を増すようになった。同時に、多くの移民グループは郊外に追いやられており、物理的にも概念的にもマージナライズされているという現状だ。
Interferencesの展示に参加したアーティストの一人が写真家のアブデル・クエタ・タヴァレス(Abdel Queta Tavares)は、西アフリカのギニアビサウ出身。14歳の時、家族でポルトガル・リスボンに移住し、その後10年間をリスボンで過ごした。現在はロンドンを拠点に活動するアーティスト。Interferencesでは、彼の代表的な作風である4枚のポートレート写真が展示されていた。2016年、真っ赤な帽子を被ったユニークなスタイルでロンドンの街を歩いていた彼に、イギリス人写真家デーヴィッド・カンター(David Cantor)が目をつけ、ポートレート写真を撮影。その写真が賞を受賞し、赤の帽子を被ったクエタ・タヴァレスの写真が、ロンドンのナショナル・ギャラリーを始め、ロンドンの各地で大々的に展開された。彼自身、赤の帽子をかぶり続けているだけでなく、帽子はアイコニックなアイテムとして、彼が撮影するポートレイト写真にもしばしば登場する。

Abdel Queta Tavaresによる作品
Interferencesは空間・都市は誰のものか、誰が未来のストーリーを形成するのか、都市のアイデンティティとはなにか、文化の役割とはなにかといったような一連の問いを私たちに投げかける。ヒップホップ・ミュージックや、ストリート・アート、クリエイティブな住居デザインのようなアーティストやデザイナーの創造力が生み出す「ソリューション」は、私たちをインスパイアする役割がある。一方で、行政や既存のシステムが、多様性とインクルーシブさに欠け、いかにマージナライズされたコミュニティを無視し続けているかを再認識させられる。
リスボンは観光客に人気がある都市というだけでなく、近年はノマド・ワーカーにとっての人気のデスティネーションにもなりつつある。都市は今後ますます多様化する「市民」を受け入れ、よりインクルーシブなものへと変化することを求められるだろう。maatは、これからのグローバル都市というものを考えさせる機会を与えてくれる場所だ。

—
Photos by Maki Nakata
(一部提供)
—
Maki Nakata
Asian Afrofuturist
アフリカ視点の発信とアドバイザリーを行う。アフリカ・欧州を中心に世界各都市を訪問し、主にクリエイティブ業界の取材、協業、コンセプトデザインなども手がける。『WIRED』日本版、『NEUT』『AXIS』『Forbes Japan』『Business Insider Japan』『Nataal』などで執筆を行う。IG: @maki8383